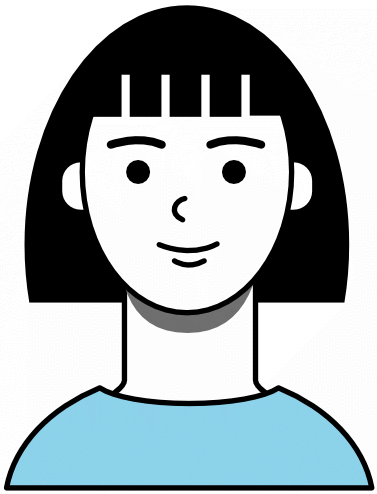top of page


年に1日だけ開扉される「東大寺・開山堂」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・開山堂」。 開山堂(国宝)は、普段非公開なので分かりづらい場所ですが、東大寺二月堂の下、四月堂の北側白壁の囲みの中にあります。 内陣中央に八角造の厨子がすえられ、秘仏・良弁(ろうべん)僧正坐像(国宝)が安置されており、年に1日、12月16日(良弁...
2021年6月5日読了時間: 2分


年に2日だけ開扉される「東大寺・俊乗堂」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・俊乗堂(しゅんじょうどう)」。 普段は非公開ですが、年に2日、7月5日(俊乗忌)、12月16日(良弁忌)のみ開扉されます。堂の中央には秘仏・重源(ちょうげん)上人坐像が安置されています。 重源上人坐像は、重源の菩提を弔うために、弟子等が造立したと...
2021年6月4日読了時間: 2分


運慶が70日で完成させた仁王像「東大寺・南大門」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・南大門」。 大仏殿へ向かう参道の途中にあり、高さ25.46mの日本最大の山門です。 天平創建時の門は平安時代の応和2年(962)に大風で倒壊。現在の門は鎌倉時代の正治元年(1199)に東大寺中興の祖・重源上人(ちょうげんしょうにん)が再建したもの...
2021年6月3日読了時間: 1分


興福寺の仏頭が本尊「山田寺跡」@奈良
奈良県桜井市にある「山田寺跡」。 現在、興福寺 国宝館で安置されている国宝・銅造仏頭は、今は頭部しか残っていませんが、かつては飛鳥山田寺の講堂本尊・丈六薬師如来像でした。その山田寺の跡地。 山田寺は、蘇我氏の一族である蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわまろ)の...
2021年6月2日読了時間: 2分


国宝仏像の所有数が日本一「興福寺・国宝館」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺」。 「古都奈良の文化財」として、東大寺や春日大社などと共に世界遺産に登録されています。 興福寺は、国宝の仏像を日本一多く所有している寺院です。 「彫刻」カテゴリーで国宝指定されている作品は全国で全136件。その中で興福寺所有の仏像は18件で、全国...
2021年6月1日読了時間: 2分


運慶の父康慶の傑作!不空羂索観音「興福寺・南円堂」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺」。 興福寺は南都七大寺の一つで、法相宗の大本山です。 興福寺の南円堂(重要文化財)は、弘仁4年(813)藤原冬嗣(ふゆつぐ)が、父の内麻呂の冥福を祈って建立されました。 現在の建物は、江戸時代中期の寛政元年(1789)に再建されたものです。...
2021年5月31日読了時間: 2分


運慶の傑作!無著・世親菩薩立像「興福寺・北円堂」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺」。 興福寺は南都七大寺の一つで、法相宗の大本山です。藤原氏の祖・藤原鎌足とその子・藤原不比等ゆかりの寺院で、藤原氏の氏寺です。 興福寺の北円堂(国宝)は、藤原不比等の1周忌にあたる養老5年(721)8月に、元正天皇の命で長屋王によって建立されまし...
2021年5月30日読了時間: 2分


普段は非公開「興福寺・五重塔と三重塔」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺」。 古都奈良のシンボルでもある興福寺の五重塔は、天平2年(730)に藤原不比等の娘、光明皇后の発願で建立されました。 現在の塔は、応永33年(1426)頃に再建されたものです。 創建当初は、各層に水晶の小塔と垢浄光陀羅尼経(くじょうこうだらにきょ...
2021年5月29日読了時間: 2分


藤原氏の氏寺「興福寺・東金堂」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺(こうふくじ)」。 東大寺や春日大社が近くにあり、近鉄奈良駅からも徒歩圏内なので、奈良観光のメインといってもいいお寺です。 興福寺の前身である「山階寺(やましなでら)」は、天智8年(669)に、藤原鎌足が重い病気を患った際に、夫人である鏡女王が夫の...
2021年5月28日読了時間: 2分


藤原氏の氏神「春日大社」@奈良
奈良県奈良市にある「春日大社」。 奈良時代の神護景雲2年(768)、神山である御蓋山(みかさやま)の麓に、称徳天皇の勅命により、武甕槌命(タケミカヅチノカミ)、経津主命(フツヌシノミコト)、天児屋根命(アメノコヤネノミコト)、比売神(ヒメガミ)の4柱の御本殿が造営されたのが...
2021年5月27日読了時間: 2分


日本最古の神社「石上神宮」@奈良
奈良県天理市にある「石上(いそのかみ)神宮」。 日本最古の神社の一つで、古代豪族・物部氏の総氏神でもあり、大和朝廷の武器庫だったと記録も残る大和屈指の古社です。 主祭神は布都御魂大神(フツノミタマノオオカミ)で、神剣「韴霊(ふつのみたま)」に宿る御霊威のことです。...
2021年5月26日読了時間: 2分


中臣鎌足の安全地帯「気都和既神社」@奈良
奈良県明日香村にある「気都和既(けつわき)神社」。 創建年や由緒は不明なことが多いようですが、境内にある看板によると以下の通り。 「気都和既神社ともうこの森」 境内は「もうこの森」と呼ばれており、この気都和既神社には、気津別命と尾曽・細川両大字の神社にそれぞれ祀られていた天...
2021年5月25日読了時間: 2分


大化改新の談合の地「談山神社」@奈良
奈良県桜井市にある「談山(たんざん)神社」。 中臣鎌足(後の藤原鎌足)と中大兄皇子(後の天智天皇)が、大化元年(645)の5月に多武峰(とうのみね)の山中に登って「大化改新」の談合を行い、後にこの山を「談い山(かたらいやま)」「談所ヶ森」と呼び、それが談山神社の名前の由来と...
2021年5月24日読了時間: 3分


神武天皇をお祀りする「橿原神宮」@奈良
奈良県橿原市にある「橿原(かしはら)神宮」。 御祭神は初代天皇・神武天皇と皇后の媛蹈鞴五十鈴媛命(ヒメタタライスズヒメノミコト)です。 神武天皇は、天照大御神の孫で天孫降臨した瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の曽孫にあたり、皇后の媛蹈韛五十鈴媛命は、大国主神の子である事代主神(コ...
2021年5月22日読了時間: 1分


鬼退治の桃太郎伝説「吉備津神社」@岡山
岡山県岡山市にある「吉備津(きびつ)神社」。 創建の詳細は不明ですが、第十六代・仁徳天皇が吉備海部直の娘である黒媛を慕ってこの地に行幸したときに、吉備津彦命の功績を聞き称えるために社殿を創建してお祀りしたのが起源と伝わるそうです。...
2021年5月20日読了時間: 2分


人魚の肉を食べた娘伝説「粟嶋神社」@鳥取
鳥取県米子市にある「粟嶋(あわしま)神社」。 標高36mの小高い丘(明神山)にあり、かつては中海に浮かぶ小さな島でしたが、江戸時代に埋め立てされ陸続きになりました。 御祭神は少彦名命(スクナヒコナノミコト)。 神代の昔、大国主神と共にこの国を開き、人々に医療の知識を教え、ま...
2021年5月19日読了時間: 2分


黄泉の国との境界「揖屋神社」@島根
島根県松江市にある「揖屋(いや)神社」。 揖夜神社の創建の詳細は不明ですが、古事記には「伊賦夜坂(いふやざか)」についての記述があり、日本書紀には「言屋社(いふやのやしろ)」、出雲国風土記には「伊布夜社(いふやのやしろ)」の記述があり、少なくとも平安朝以前には広く知られてい...
2021年5月18日読了時間: 1分


火の発祥地「熊野大社」@島根
出雲大社と並ぶ、出雲国一の宮である「熊野大社」。 松江の市街地から離れた静かな山間地にあります。 御祭神は、伊邪那伎日真名子 加夫呂伎熊野大神 櫛御気野命。 長いお名前ですが、須佐之男命(スサノヲノミコト)のことです。 伊邪那伎日真名子(いざなぎのひまなこ)=父神である伊邪...
2021年5月14日読了時間: 1分


大国主神の国譲り「出雲大社」@島根
島根県出雲市にある「出雲大社」。 御祭神は、出雲に大国をつくった国づくりの神、大国主神(オオクニヌシ)です。 古事記によると、大国主神が天照大神に「国譲り」した際、その代償として壮大な御神殿が創建され、大国主神をお祀りしたのが出雲大社の起源とされています。...
2021年5月12日読了時間: 2分


日本の夜を守る「日御碕神社」@島根
島根県出雲市にある「日御碕(ひのみさき)神社」。 「出雲国風土記」に「美佐伎社」と記される歴史ある神社です。 下の宮「日沈宮(ひしずみのみや)」と上の宮「神の宮」の上下二社からなり、両本社を総称して「日御碕神社」と呼ばれます。...
2021年5月10日読了時間: 2分
bottom of page