運慶の傑作!無著・世親菩薩立像「興福寺・北円堂」@奈良
- Asami

- 2021年5月30日
- 読了時間: 2分
更新日:2021年7月5日

奈良県奈良市にある「興福寺」。
興福寺は南都七大寺の一つで、法相宗の大本山です。藤原氏の祖・藤原鎌足とその子・藤原不比等ゆかりの寺院で、藤原氏の氏寺です。
興福寺の北円堂(国宝)は、藤原不比等の1周忌にあたる養老5年(721)8月に、元正天皇の命で長屋王によって建立されました。
治承4年(1180)の被災(=南都焼討)後、承元4年(1210)頃に再建されました。
三重塔と共に興福寺で最古の建物。
南都七大寺
奈良時代に朝廷の保護を受けた平城京およびその周辺の七つの大寺。
東大寺、興福寺、元興寺、大安寺、薬師寺、西大寺、法隆寺。
第44代・元正天皇
父は天武天皇と持統天皇の子である草壁皇子、母は第43代・元明天皇。
独身で即位した初めての女性天皇。次代は聖武天皇。
長屋王
父は天武天皇の長男の高市皇子、母は天智天皇の皇女の御名部皇女。
藤原不比等の4人の息子、藤原四兄弟の陰謀により、長屋王の変で自殺。
その後、藤原四兄弟は4人とも揃って病死したため、長屋王の祟りではないかと噂される。

本尊 弥勒如来坐像(国宝・鎌倉時代)
現在の堂内には、本尊である弥勒如来坐像を中心に、無著(むじゃく)・世親(せしん)立像をはじめとして、木心乾漆四天王立像などが安置されています。
弥勒如来坐像の台座内枠には源慶、静慶、運賀、運助、運覚、湛慶、康弁、慶運、康勝ら慶派仏師の名が墨書されています。彼らを統率していたのが運慶で、運慶晩年の名作として知られます。

無著立像(国宝・鎌倉時代)194.7cm
釈迦入滅後約千年を経た5世紀頃、北インドで活躍し、法相教学を確立した兄・無著と弟・世親の兄弟像。
無著像は老人の顔で右下を見、世親像は壮年の顔で左を向き遠くを見ています。
運慶の指導のもとに無著像は運助、世親像は運賀が担当しています。

世親立像(国宝・鎌倉時代)191.6cm
興福寺北円堂は普段は非公開で、春季・秋季のみ特別開帳されます。
無著・世親菩薩立像は、運慶の傑作仏として超有名でファンが多く、その写実性、堂々としたたくましさ質量感、とにかくカッコイイ仏像です。
北円堂の特別開帳には何度か通っていますが、何度拝見しても惚れ惚れします。
<法相宗大本山 興福寺・北円堂>
【住所】奈良県奈良市登大路町48
【電話】0742-22-7755
【時間】9:00〜17:00 ※春季、秋季のみ特別開帳
【拝観料】北円堂特別公開 大人300円/中高生200円/小学生100円
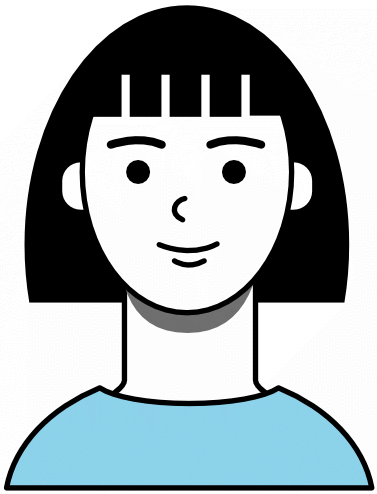



コメント