鬼退治の桃太郎伝説「吉備津神社」@岡山
- Asami

- 2021年5月20日
- 読了時間: 2分

岡山県岡山市にある「吉備津(きびつ)神社」。
創建の詳細は不明ですが、第十六代・仁徳天皇が吉備海部直の娘である黒媛を慕ってこの地に行幸したときに、吉備津彦命の功績を聞き称えるために社殿を創建してお祀りしたのが起源と伝わるそうです。
御祭神は、吉備津彦命(キビツヒコノミコト)。
第七代・孝霊天皇の皇子「倭五十狭芹彦(ヤマトヰサセリヒコ)」の別名。第十代・崇神天皇の御代に四道将軍の一人に任命され、現在の吉備津神社の場所に本陣を構え、吉備国を平定したことから、吉備津彦命と呼ばれるようになりました。
吉備国の平定の際、温羅(うら)=吉備地方に伝わる古代の鬼を退治したことから、桃太郎のモデルといわれています。





矢置石
吉備津彦命が鬼退治の際に、矢を置いたと伝わる石。



本殿・拝殿(国宝)
応永32年(1425)に足利義満によって再建されました。
建築様式は「比翼入母屋造」。全国唯一の様式から「吉備津造」とも称されます。

廻廊
天正7年(1579)に再建されました。
全長360mにもおよび、自然の地形そのままに一直線に建てられています。

御釜殿(重要文化財)
慶長17年(1612)に再建されました。
吉備津彦命が退治した鬼の首が埋めてあるという伝承があり、釜が鳴る音によって吉凶を占う「鳴釜神事」は古来より全国に知られています。
江戸時代、上田秋成の雨月物語の中にも「吉備津の釜」として一遍の怪異小説が載せられています。
「鳴釜神事」の起源は、吉備津彦命の温羅(鬼)退治のお話に由来します。
吉備津彦命は捕らえた温羅の首をはねて曝しましたが、不思議なことに温羅は大声をあげ唸り響いて止むことがありませんでした。
そこで困った吉備津彦命は、家来に命じて犬に喰わせてドクロにしても唸り声は止まず、ついには当社のお釜殿の釜の下に埋めてしまいましたが、それでも唸り声は止むことなく近郊の村々に鳴り響きました。
吉備津彦命は困り果てていた時、夢枕に温羅の霊が現れて、『吾が妻、阿曽郷の祝の娘阿曽媛をしてミコトの釜殿の御饌(そなえもの)を炊がめよ。もし世の中に事あれば竃の前に参り給はば幸有れば裕に鳴り禍有れば荒らかに鳴ろう。ミコトは世を捨てて後は霊神と現れ給え。われは一の使者となって四民に賞罰を加えん』とお告げになりました。
吉備津彦命はそのお告げの通りにすると、唸り声も治まり平和が訪れました。
御釜殿で、この神事に仕えているお婆さんを阿曽女(あぞめ)といい、温羅が寵愛した女性といわれています。“鬼の城”の麓に阿曽の郷があり、代々この阿曽の郷の娘がご奉仕しているそうです。



<吉備津神社>
【住所】岡山県岡山市北区吉備津931
【電話】086-287-4111
【時間】8:30〜16:00(受付・授与所)
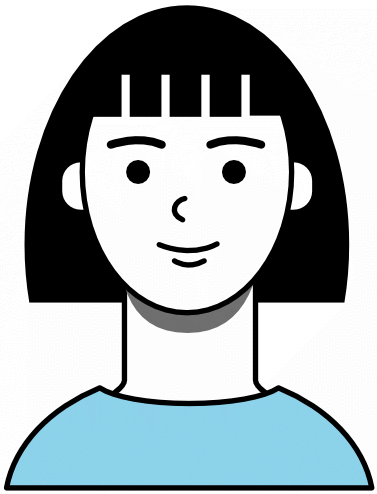



コメント