大化改新の談合の地「談山神社」@奈良
- Asami

- 2021年5月24日
- 読了時間: 3分

奈良県桜井市にある「談山(たんざん)神社」。
中臣鎌足(後の藤原鎌足)と中大兄皇子(後の天智天皇)が、大化元年(645)の5月に多武峰(とうのみね)の山中に登って「大化改新」の談合を行い、後にこの山を「談い山(かたらいやま)」「談所ヶ森」と呼び、それが談山神社の名前の由来となりました。
ちなみに日本で最初の元号が「大化」で、645年に乙巳の変に始まる一連の国政改革「大化改新」により、新たな時代の始まりとして元号が定められました。
御祭神は藤原鎌足です。
藤原鎌足(614〜669年)は藤原氏の始祖で、鎌足の次男が藤原不比等です。
談山神社の創建は藤原鎌足の没後、長男の定慧和尚が留学中の唐より帰国し、摂津国阿威山から父の由縁深い多武峰に墓を移し、天武天皇7年(678)に木造十三重塔を建てたことが始まりとされます。



神廟拝所(重要文化財)
秘仏の談峯如意輪観音菩薩坐像や鎌足公御神像などが安置されています。羅漢や天女の姿が描かれた内部の壁画なども見どころ。

秘仏・談峯如意輪観音菩薩坐像(鎌倉時代)
普段は非公開ですが、観音講まつりの期間中(6~7月)のみ一般公開されます。
三脚を使用しなければ写真撮影も可能。ありがたい。美しいです。

鎌足公御神像(江戸時代)
もともと飛鳥の藤原寺でお祀りされていたものを明治の廃仏毀釈の際、藤原寺が廃寺になると同時に、談山神社の総社本殿に移座されました。 現在、談山神社本殿にお祀りされている鎌足公御神像ではありません。

神廟拝所の内部の壁画

総社拝殿(重要文化財)
長寿をもたらす七福神の「福禄寿」が祀られています。

総社拝殿の福禄寿



十三重塔(重要文化財)
現存する世界で唯一の木造の十三重塔で、談山神社のシンボル。
天武天皇7年(678)、定慧が父・鎌足を慰霊するために建立されました。

楼門(重要文化財)

拝殿(重要文化財)
楼門や本殿と回廊でつながった1520年造営の拝殿。
三脚を使用しなければ写真撮影も可能。

本殿(重要文化財)
藤原鎌足を祀る三間社隅木入春日造の本殿。
701年の創建で、現在の建物は1850年に建て替えられました。日光東照宮の造営のお手本にもなった絢爛豪華な朱塗りの建物。




摂社・東殿(重要文化財)
優れた歌人で情熱的な恋の歌を詠んだ鎌足の正妻・鏡女王(かがみのおおきみ)をお祀りしています。縁結びの神様として有名で「恋神社」とも呼ばれています。
鏡女王の素性については謎に包まれていますが、はじめは天智天皇の妃で、後に藤原鎌足の正妻となります。恋の歌の達人でミステリアスなところも含めて想像をかき立てられますね。
<万葉集の一首>
神奈備の 石瀬の杜の 呼子鳥 いたくな鳴きそ 我が恋まさる by 鏡王女
(かんなびの いわせのもりの よぶこどり いたくななきそ わがこいまさる)
訳:神奈備の石瀬の森に鳴く呼子鳥よ、そんなに激しく鳴かないでおくれ。恋しさがつのるから。
神奈備=神が宿る場所。
石瀬の森=奈良県生駒郡斑鳩にある森。
呼子鳥=人を呼ぶような声で鳴くという。
ちなみに、藤原不比等は鎌足と鏡女王の子ですが、天智天皇の落とし胤(だね)という説もあるようです(妊娠中の鏡女王を鎌足に下げ渡した説)。
実質、藤原氏の繁栄は不比等以降であるし、その説を不比等自身が吹聴したのかもしれません。大化改新前までは仏教排撃派だった鎌足が長男の定慧を出家させ、唐に留学させたのも不思議ですし、何か出生の秘密と関係あるのかも?しれません。

鏡女王像

むすびの岩座
この石をなでると人間関係や恋愛などの結びの願い事が叶うとか。
<談山神社>
【住所】奈良県桜井市多武峰319
【電話】0744-49-0001
【時間】8:30〜16:30
【拝観料】大人600円/小人300円
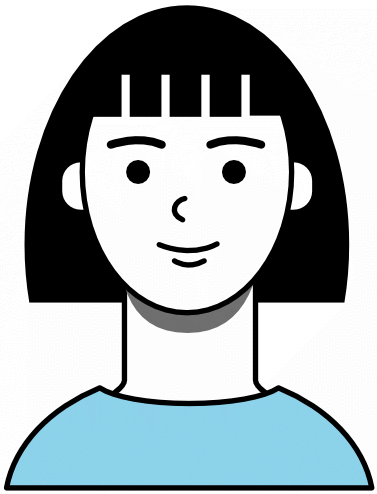



コメント